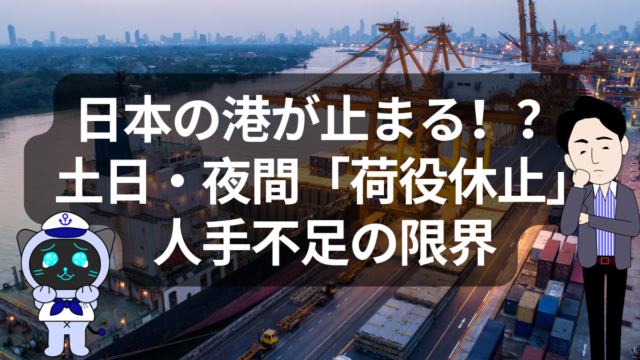投稿日:2025.07.14 最終更新日:2025.07.14
日本造船業、鋼材価格の国際格差が収益圧迫!中国・韓国との競争力に大きな差
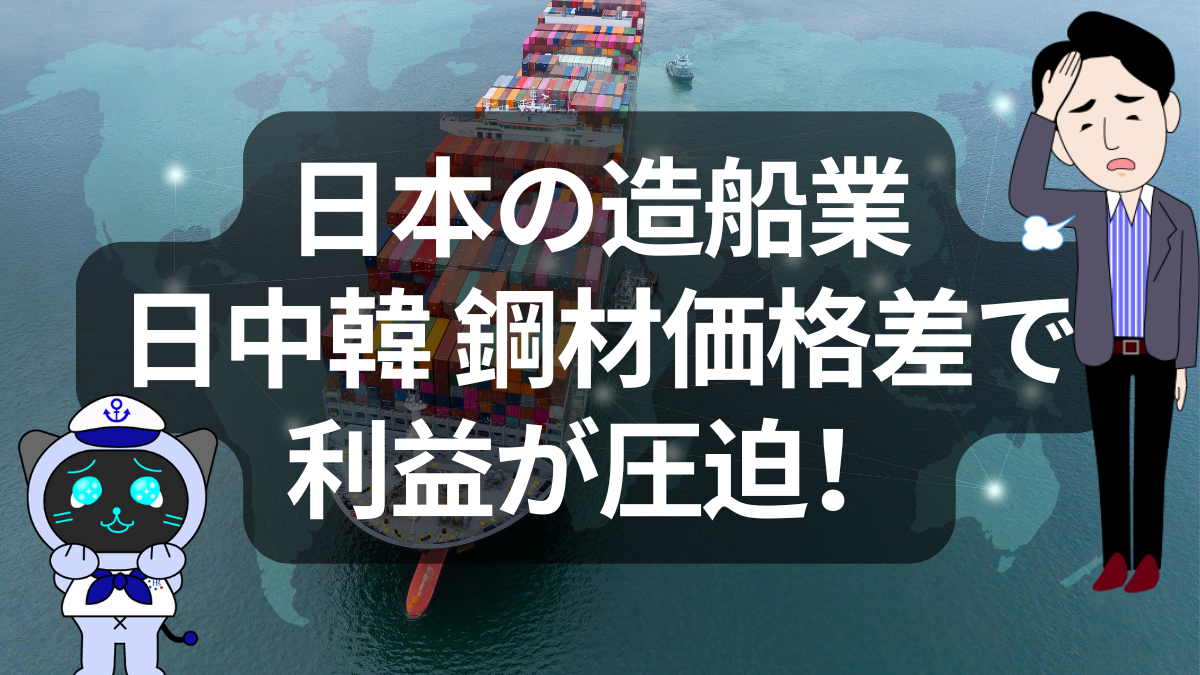
今回は「鋼材価格の内外格差」という、造船業界にとって極めて重要なテーマを取り上げます。
いま、日本の造船所は人手不足に続く深刻なコスト課題に直面しています。それが、高止まりする国内の鋼材価格です。
CONTENTS
鋼材価格、国内は高止まり・海外は下落
日本の造船用厚板(鋼材)は、1トンあたり10万円超で推移中。
一方、中国では6〜7万円、韓国では7〜8万円台と、日中・日韓で1〜2割以上の価格差が生じています。
この差は、船1隻あたり数億〜10億円規模のコスト差になる可能性があると指摘されています。
なぜここまで差が生まれたのか?
1. 中国の“激安価格”の背景
中国では、鋼材を毎月の入札で最安メーカーから調達。 さらに政府の補助金政策が製造コストの13〜20%を下支えしているとの分析もあります。 結果として、驚異的な安さで鋼材を確保できているのです。
2. 韓国も中国産を2〜3割利用
韓国の造船所では、厚板の2〜3割を中国から輸入しており、自国鋼材の価格も低下傾向。これにより、コスト競争力を大幅に強化しています。
日本造船所はなぜ厳しいのか?
日本では国内調達が基本であり、安全性や品質を重視して中国産の採用に慎重です。
その結果、価格差がそのまま造船コストに反映される構造となっています。
最近では、中国造船所が短納期・低価格の案件を受注するケースも増え、船価にも差が出始めています。
円安の恩恵も限界に
これまで円安や高船価によって利益を確保してきた日本の造船業界ですが、「1ドル=130円超の円高では、現行の受注残では採算が厳しい」という声も出ています。
つまり、為替の変動に耐えられない構造的弱さが、今まさに露呈しているのです。
政府と業界の再編・対策も進行中
2024年には今治造船がJMUを子会社化し、業界再編が加速。
政府もこれに合わせ、
・官民ファンドによる1兆円規模の支援構想 ・国内鉄鋼流通の最適化支援
といった施策を検討中です。
また、米国でも日本企業による米鋼材会社の買収承認など、グローバル競争力を高める支援の動きが見られます。
イーノの視点:この差は“静かなる構造リスク”
正直、物流や造船に関わっていない人には「鋼材価格の差なんて大したことない」と思われがちかもしれません。
しかし、1隻で10億円の差が出る世界です。これは決して無視できる問題ではありません。
これから必要なのは、
・国内鋼材の共同購買や価格交渉の見直し ・品質を担保した上での海外鋼材の戦略的活用 ・政府・造船・鉄鋼業界の連携による競争力強化
この3つの方向性が鍵になると考えています。
まとめ
今後、新造船需要が落ち着いたとき、この鋼材価格差が大きな重荷になるリスクは非常に高いです。
これまで日本造船業界は為替や船価の追い風に助けられてきました。
しかしこれからは、“構造をどう変えるか”が問われる時代に入っています。