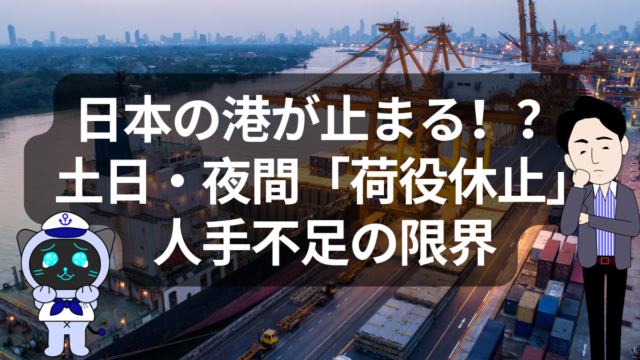投稿日:2025.08.27 最終更新日:2025.08.28
2026年以降のコンテナ輸送、市場はどう動く?供給過剰と戦略転換の時代へ

J.P.モルガンの最新レポートによると、2026年以降、コンテナ海運業界は供給過剰の時代に突入する見込みです。
本記事では、その現実と荷主・船会社それぞれの影響について解説します。
CONTENTS
供給過剰の現実
コロナ禍の反動で新造船の大量発注が続いた結果、それらが2026年以降に一気に稼働し始めます。
これは2009年以来の大規模な発注残であり、世界の船腹量は今後数年で30%増加する可能性も。
紅海危機や港湾混雑による一時的な供給制限は落ち着きつつあり、「隠れていた供給過剰」が徐々に顕在化しています。
荷主にとっての光と影
運賃が下がることは、荷主にとっては歓迎されます。特にアメリカでは、トランプ関税によるコスト増を緩和する要因となります。
コロナ期の「高運賃+低信頼性」から脱却できるのもメリットです。
ただし、運賃下落を抑えるために船会社が取る戦略――
・欠航(ブランクセーリング)
・減速運航(スロースチーミング)
これにより納期は不安定になり、「安いけど不便」という新時代に突入する可能性があります。
船会社の本音と戦略
船会社にとっての教訓は、「信頼性に投資しても市場は報われない」という経験です。
コロナ期、信頼性は最低でも利益は過去最高でした。つまり市場は運賃だけを評価してきたのです。
そのため、今後は以下の動きが主流になります。
・信頼性より収益性を重視
・老朽船のスクラップ加速
・ネットワーク再編
・港湾混雑さえも「供給調整の味方」とみなす
J.P.モルガンによれば、港湾混雑によって市場から消えている船腹は全体の約4%。これはコロナ前の2%より増加しており、供給過剰の緩和に一役買っています。
マクロ経済と成長率の鈍化
2025年前半は、関税前倒し需要により4.5%成長を記録しました。
しかし第3四半期は1.8%成長、第4四半期は横ばいと見込まれています。
2026年以降は年間2%程度の成長に落ち着く予測です。
一方、供給は以下のように増加する見通しです:
・2025年:6.5%増
・2026年:9%増
需給ギャップの拡大により、運賃はさらに下押しされる可能性が高いです。
まとめ
2026年以降のコンテナ海運の構図は次の通りです。
運賃は安くなる → 荷主にはメリット。 納期やリードタイムは不安定 → サプライチェーンにはリスク。 船会社は収益性を優先 → 信頼性投資は限定的。
荷主にとっては「価格だけ見て安心するな」という時代です。
輸送戦略では、運賃だけでなくリードタイムや欠航リスクも考慮すべきです。
私たちフォワーダーとしても、こうした市況を踏まえた現実的な提案が求められています。