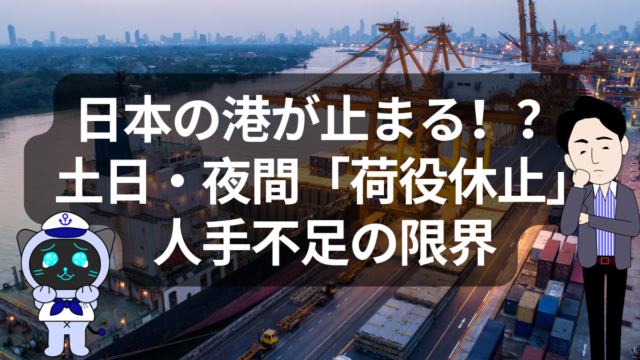投稿日:2025.08.28 最終更新日:2025.08.29
国土交通省、造船サプライチェーン強化で海事産業支援へ

国土交通省海事局が2026年度予算の概算要求で、約96億円を計上しました。
その中で特に注目されているのが、「造船の強靭なサプライチェーン構築」です。
ただし、現時点では「事項要求」という形。
つまり、具体的な金額や中身はまだ決まっておらず、今後の予算編成の過程で詳細を詰めていく状況です。
CONTENTS
背景にある日米協力
この動きの背景には、日米関税交渉があります。
経済安全保障の観点から、両国が「造船でも協力を深めていこう」という合意に至っています。
ただし、実際にどのような協力が行われるかは不透明です。
政府系金融機関を通じた出資や、造船所への技術支援といった可能性が検討されています。
海事クラスターの強化
さらに、政府の「骨太の方針2025」でも掲げられているように、国交省は海運・造船を中核とする海事クラスター全体の強化に力を入れています。
造船だけでなく、以下の施策も盛り込まれています:
・内航船の技術開発や省人化
・舶用機器のDX化
・自動運航船の制度整備
・海事人材の育成(JMETSの練習船や教育設備の更新)
国際競争の現実
なぜここまで力を入れるのか?理由はやはり国際競争です。
世界の造船業を見れば、中国と韓国が圧倒的なシェアを持っています。
特に新燃料船、たとえばLNG焚きやメタノール対応船の発注が相次いでおり、韓国の現代重工やサムスン、中国のCSSCは巨額受注を続けています。
一方、日本の造船所は今治造船やJMUが中心ですが、船台はすでに2028年まで埋まっている状況です。
納期競争では出遅れやすく、国が後押ししないと国際的に存在感を保てません。
GHG削減への対応
もう一つの背景はGHG削減です。
IMO(国際海事機関)では中期対策が承認され、CO₂排出削減のための課金やインセンティブ制度が導入されます。
造船業界も環境対応を避けられず、新燃料船や効率化技術の開発に資金が必要です。
国が制度設計を進めて支援する流れになっています。
まとめ
「日本は造船立国だ」と言われた時代もありましたが、現在は競争が熾烈です。
今回の予算要求は、その巻き返しの第一歩といえるでしょう。