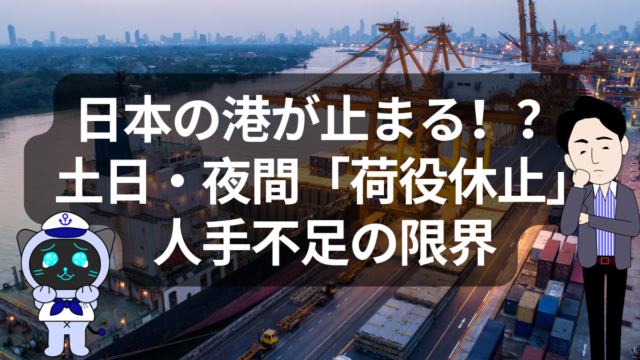投稿日:2025.09.02 最終更新日:2025.09.02
世界の港湾混雑Q2レビュー:欧州は慢性化、アジアは明暗、北米は安定

今日は「世界の港湾混雑、第2四半期のレビュー」をテーマにお話しします。
世界中の港って、実は地域ごとにだいぶ状況が違うんですよね。
CONTENTS
全体の流れ
まず全体感からいくと、欧州は「混雑の慢性化」、アジアは「港によって好不調が分かれる」、北米は「需要増を何とか処理」っていう感じです。
S&Pグローバルの分析によれば、欧州は入港から出港までにかかる時間が延びていて効率低下が目立ちました。
一方で北米は平均的なコールサイズを保ちながら、到着手続き時間を短縮して捌いています。
アジアはシンガポールやポートクランは効率改善した一方、レムチャバンやカイメップは悪化するなど、明暗が分かれる状況です。
欧州:なぜ混雑が長引くのか
ここが一番のポイントです。
ヨーロッパは単なる「作業が遅れている」ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っているんです。
紅海迂回の影響:スエズを避けて喜望峰まわりの航路が長期化し、入港スケジュールが乱れています。
その結果、一気に船が押し寄せる“同時到着”が発生し、港で詰まりが生じています。
労働環境の制約:港湾労働のストライキや協約更新で、一時的に人手が不足するケースも。
内陸輸送のボトルネック:鉄道工事や河川の水位低下により港から貨物が出せない → ヤードに滞留 → 新たな船が受け入れにくいという悪循環です。
インフラの限界:超大型船の寄港が常態化し、荷役ボリュームが巨大化。
岸壁の長さやガントリー台数が物理的な限界を見せています。
この複合要因により、欧州港は慢性的な混雑から抜け出せずにいるわけです。
アジアの港湾 混雑状況
アジアは混在型です。
シンガポール、タンジュン・ペラパス、マニラ、ポートクランは効率が改善されています。
逆に、レムチャバン、カイメップ、チャトグラムは混雑が悪化しています。
この差は、基幹航路からのトランシップ比率や港湾インフラ投資の有無によって生じています。
北米の港湾 混雑状況
北米は比較的安定しています。
ロングビーチ港では一部コールサイズは減少したものの、船の本数増加で総量を捌く形に。
さらに、2029年に向けて3億6500万ドル規模の改良工事を進行中。
18,000TEU級の船を同時に2隻受け入れるためのハード投資が進められています。
まとめ
第2四半期の世界港湾レビューをまとめると:
・欧州は紅海迂回や内陸輸送の影響もあり、慢性的な混雑が継続
・アジアは港によって状況が大きく異なる
・北米は投資を進めつつ安定を維持
物流の現場にいる私たちにとって、「港はいつでも止まる可能性がある」という前提で動くしかありませんね。