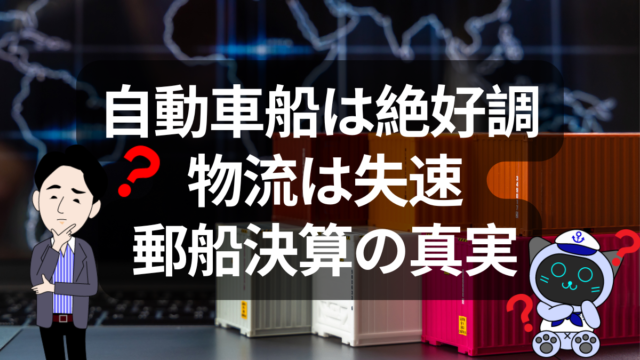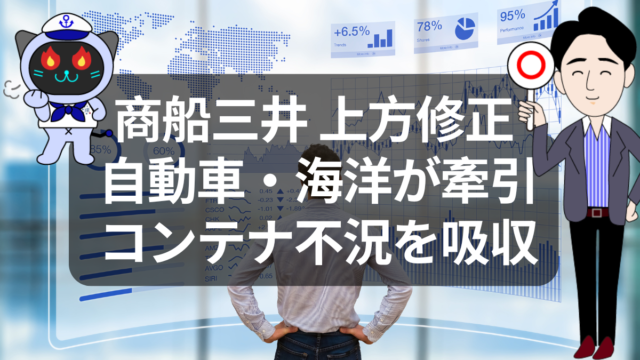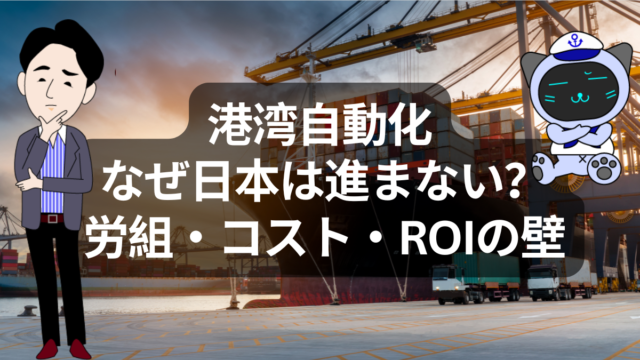投稿日:2025.09.04 最終更新日:2025.09.04
苫小牧港の収支改善と労働力不足でクレーン稼働を縮小!

今日は北海道の物流の要、苫小牧港で起きている収支改善の動きと全国的課題についてお話しします。
CONTENTS
苫小牧港の現状と収支改善策
苫小牧港を運営するTICT(苫小牧国際コンテナターミナル)は、経営悪化を受けて10月から運営体制を見直すと発表しました。
主な変更点は以下の2つです:
- RTG(ガントリークレーン)の稼働を5基から4基に削減
- コンテナ船の同時受け入れを3隻から2隻に縮小
要するに、オペレーションの規模を縮小し、コストを削減するという判断です。
しかしその結果、船の待機時間やトラックの搬出入の滞留が発生する懸念が高まっています。
苫小牧港は北海道全体の約8割のコンテナを取り扱う物流の大動脈。ここにボトルネックが生じれば、道内の産業や生活全般に直接的な影響が出るおそれがあります。
背景にある「全国的な労働力不足」
今回の問題は、苫小牧だけに限った話ではありません。
全国的に港湾労働者の不足が深刻化しており、荷役作業の効率が低下しています。
調査によると、日本企業の約6割が労働力不足で深刻な影響を受けていると回答。さらに、2040年には1,100万人の労働力が不足するという試算もあります。
特に北海道は地理的制約も加わり複雑です。
苫小牧のコンテナターミナル(東港区)とRORO船・フェリーの拠点(西港区)は約20km離れており、作業員の効率的配置が難しいという構造的な問題もあります。
何が必要か?
今回の縮小策は「やむを得ないコスト抑制策」ですが、長期的には限界があります。
港の機能を維持するためには、以下の取り組みが不可欠です:
- ユーザーへの適正な料金転嫁
- 港湾オペレーションの自動化・DX推進
- 労働条件の改善と人材確保
まとめ
苫小牧港は北海道の物流ライフライン。
ここが滞れば、食品・工業製品・生活物資のすべてに影響を及ぼします。
だからこそ、単なる経費削減で終わらせるのではなく、持続可能な体制づくりが強く求められています。