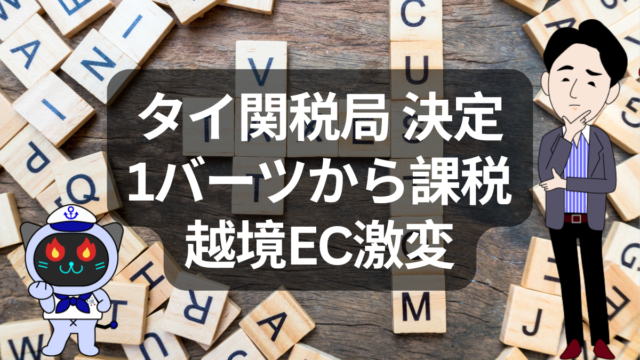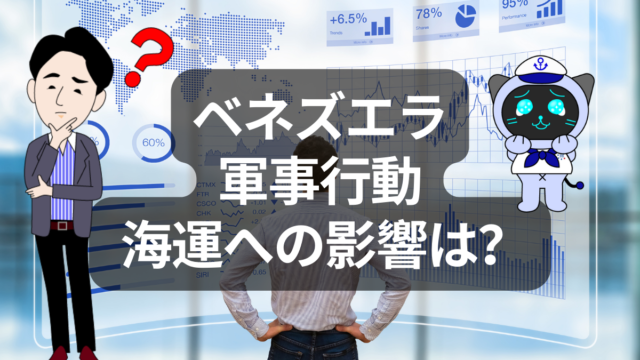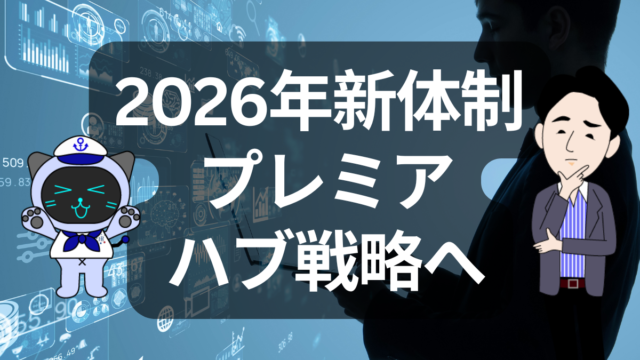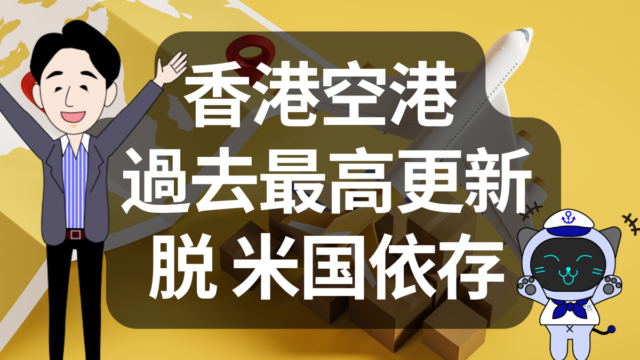投稿日:2025.09.25 最終更新日:2025.09.25
通関業務の価格転嫁と新しいビジネスモデル!
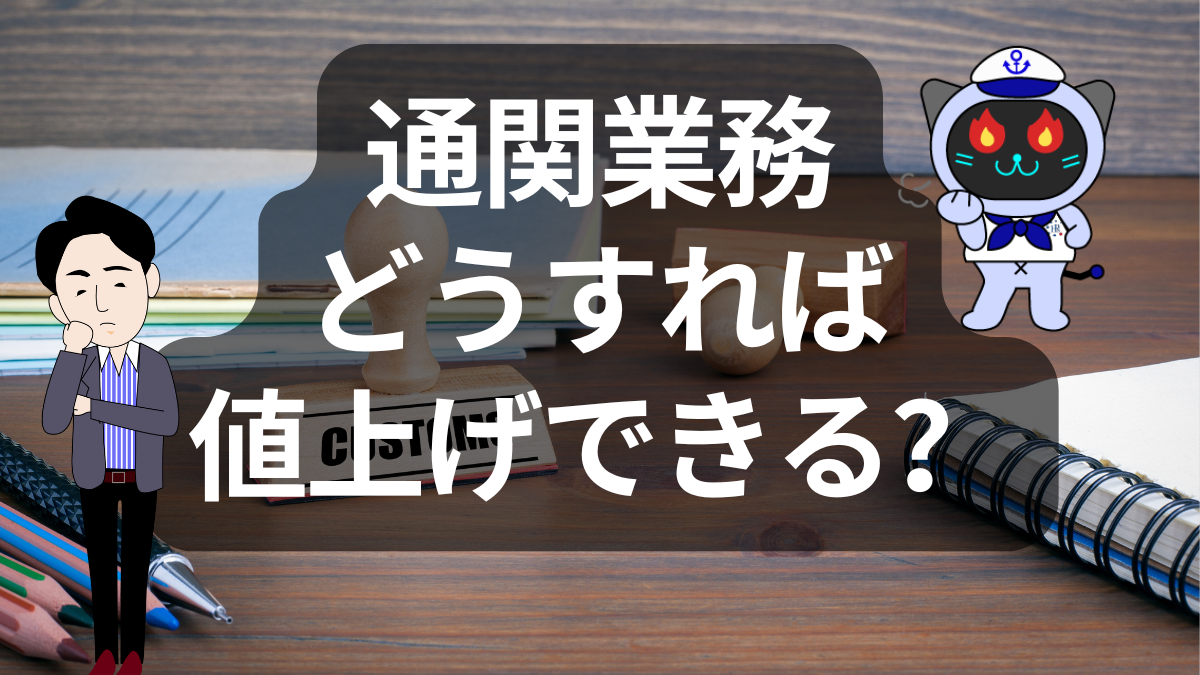
今日は「通関業界の価格転嫁と新しいビジネスモデル」についてお話しします。
9月19日、日本通関業連合会(通関連)の岡藤正策会長が、国土交通省の「次期総合物流施策大綱」に関する検討会で発表しました。
そこで強調されたのは「通関業務における価格転嫁の必要性」です。
CONTENTS
案件増えるが価格は据え置き
実際、越境ECの拡大で輸入許可件数は2024年に1億9000万件。2016年の6倍以上です。
一方で、通関業の収入はこの20年間ほぼ横ばいで1100億円前後で推移。
人件費や維持管理コストは上がり続けているのに、料金に転嫁できていないのが実情です。
特に中小事業者には大きな負担となっていて、名古屋通関業会のアンケートでは、そもそも荷主と価格交渉のテーブルにつけない実態も明らかになりました。
岡藤会長は「通関業者は耐え忍びながらサプライチェーンを守ってきた」と語っています。
通関業界としての取り組み
業界としては競争力強化に取り組んでいて、例えば通関連は「EPA関税認定アドバイザー制度」を立ち上げました。
サービス高度化や人材育成を進め、荷主に正しく対応することで適正料金収受を目指しています。
さらに、荷主が関税や消費税を通関業者に立替させる問題にも言及しており、これも改善すべき課題だとしています。
通関業は財務省の所管ですが、昨年の文書では「物流業の一部」として位置付けられ、大綱の議論に正式に加わった。
これ自体も業界にとって大きな一歩です。
イーノ的視点での通関業改革
さて、ここからは僕自身の考えです。
正直「なんでも値上げ」というのは難しい。だからこそ、発想の転換が必要だと思います。
まずは案件の難易度に応じた料金設定。
簡易的な通関案件はAIやRPAに任せて低コストで処理。
逆に食品や医薬品のように規制が厳しく、例えばタイのFDA登録が必要なケースは専門性が高い分、料金も高めに設定します。
僕のタイの会社もFDA案件はあえて高めにしています。お客様も「確実に通すなら妥当」と納得してくれるんです。
次にメーカーの自社通関を支援するコンサルモデル。
ある程度の規模の企業は、通関士を自社で抱えた方が効率的な場合もあります。
そこで通関業者は「奪われる側」ではなく「支援する側」に回る。
通関体制の構築や人材教育をビジネスにするんです。教育事業との親和性も高いですね。
まとめ
通関業は厳しい環境に置かれていますが、逆に新しいモデルを打ち出すチャンスでもあります。 簡単な案件はAIで処理、難しい案件は高付加価値で対応、自社通関を支援するコンサルにも回る。 こうした仕組みで「荷主の理解を得ながら、業界全体の持続可能性を高めていくこと」が必要だと思います。