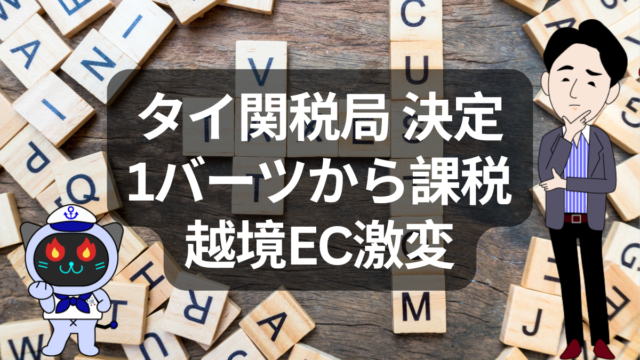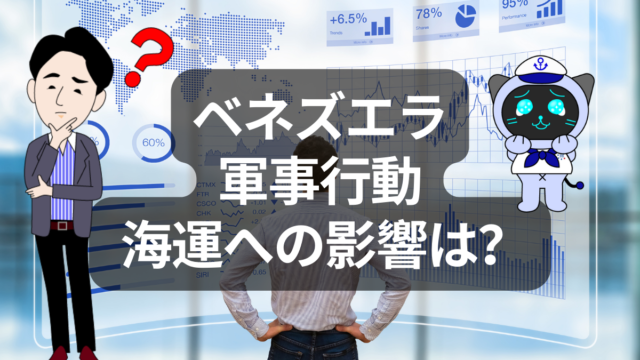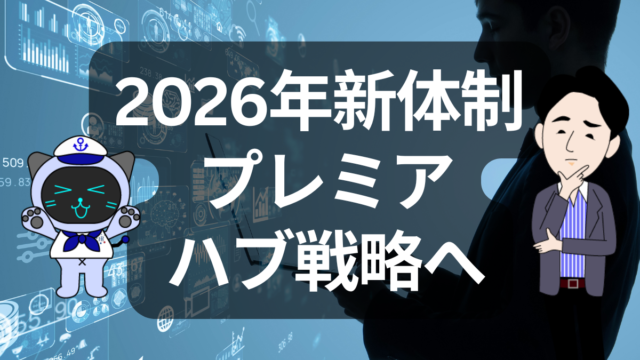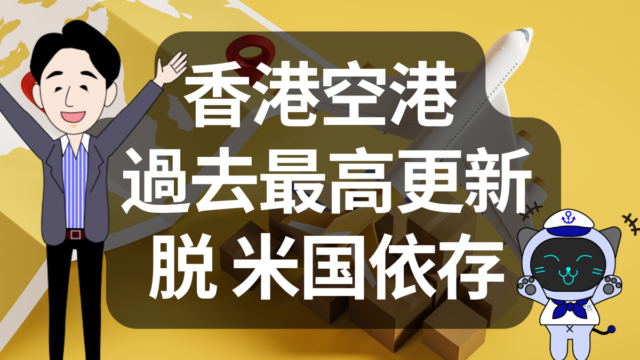投稿日:2025.09.25 最終更新日:2025.09.25
日本郵船、LCO₂輸送で「石油からCO₂へ」大転換

日本郵船が今、力を入れているのがLCO₂(液化CO₂)輸送事業です。 FPSOやシャトルタンカーで培った海洋事業のノウハウを活かし、CCS(CO₂回収・貯留)需要の高まりに応える動きが加速しています。
CONTENTS
海洋事業の拡大と新たな一手
日本郵船は2008年にFPSOやシャトルタンカーを使った海洋事業に参入。
現在ではFPSO6基、シャトルタンカー28隻を運航し、世界シェア3割を占めるトッププレイヤーとなりました。
しかし、石油需要が2030年前後にピークを迎えると言われる中、その先を見据えた成長戦略が必要です。
注目のLCO₂輸送とは?
LCO₂輸送とは、液化二酸化炭素を海上で運搬する事業です。
背景には、CO₂排出削減を目指すCCS(Carbon Capture and Storage)需要の拡大があります。
特にアジアで、CO₂を回収し、輸送し、地中に貯留するという動きが広がっています。
常温昇圧(EP)方式でエネルギー効率化
日本郵船はノルウェーのクヌッツェン社と合弁でKNCCを設立し、EP(常温昇圧)方式を用いたLCO₂輸送を開発しています。
これは、液化CO₂を常温で輸送可能にする技術で、エネルギー消費を抑え、バリューチェーン全体でのコスト削減も可能にします。
海洋事業グループへの移管の理由
当初はグリーンビジネス部門で担当していたLCO₂輸送ですが、FPSOやシャトルタンカー事業の知見を活かすため、2024年4月より海洋事業グループが主導。
石油・ガス事業で培ったネットワークや経験が、この分野でも武器になります。
FPSO事業の今後と慎重な攻め
FPSO事業も引き続き重要で、今後はガイアナ、ナミビアなど新市場での展開が期待されます。
ただし、リース案件の減少や資金調達の難しさもあり、より慎重で戦略的な対応が求められます。
まとめ:石油からCO₂へ
日本郵船は、脱炭素社会に向けてLCO₂輸送という新たな成長軸を確立しつつあります。
EP方式による輸送は、環境負荷を減らしつつ収益化も期待できる注目の技術。
石油事業の安定収益と両立しながら、持続可能な未来に向けた動きが加速しています。
今後の海運業において、「石油からCO₂へ」という流れはますます重要になっていくでしょう。