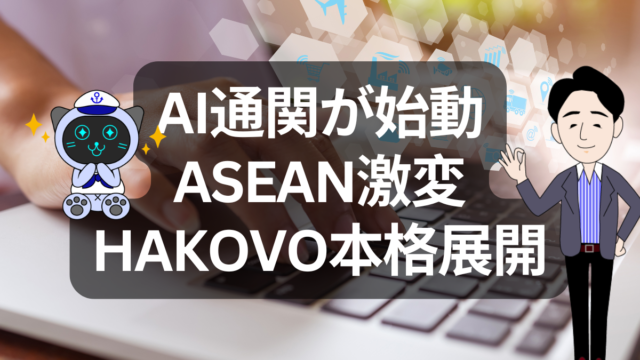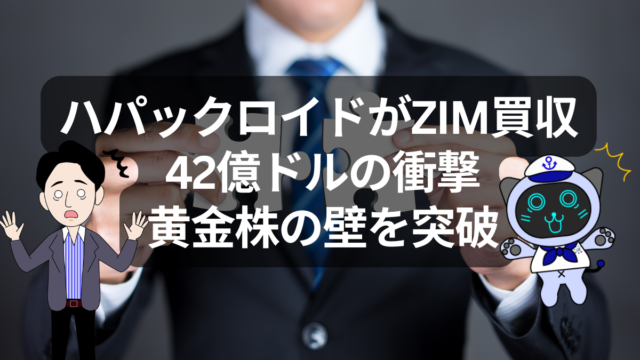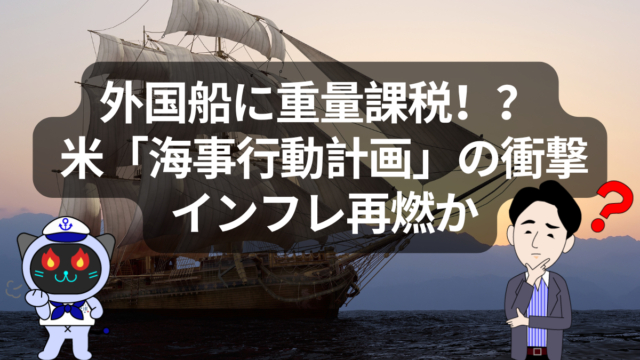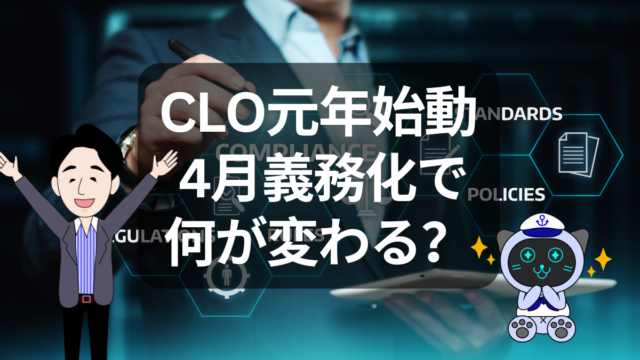投稿日:2025.10.06 最終更新日:2025.10.06
第三国経由も対象へ!反ダンピング関税の新制度と日本の通商戦略転換
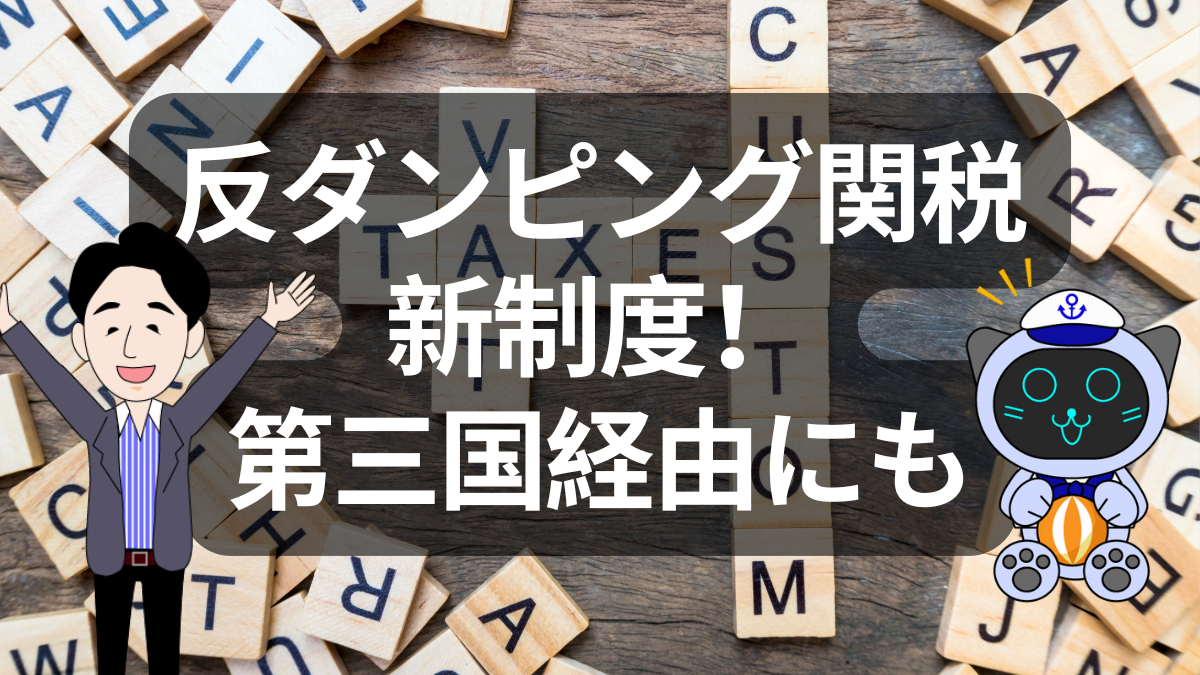
日本政府が反ダンピング関税の新制度として「第三国経由の輸入にも関税を課す仕組み」の導入を検討しています。
これまで国内産業を苦しめてきた「迂回輸出」というグレーな輸入ルートをどう封じるのか?
今回はその背景と制度の中身、そして日本の通商政策がこれからどう変化していくのかを詳しく解説します。
CONTENTS
反ダンピング関税とは何か?
反ダンピング関税とは、外国から「不当に安い価格」で輸入される商品が、国内産業に被害を及ぼすと判断された場合に、追加で課せられる関税のことです。
これはWTOが認める合法的な措置で、日本を含む多くの国が国内産業の保護を目的に活用しています。
例えば通常100円の商品が、海外から50円で大量に流入すれば、国内の同業者は到底太刀打ちできません。こうした場合に差額の50円分を課税するのが反ダンピング関税です。
なぜ今、「第三国経由」が問題なのか?
日本が中国など特定の国に反ダンピング関税を課すと、輸出企業はその対象国を直接経由せずに、東南アジア諸国などを経由して商品を輸出する手法を取るようになります。
これが「第三国経由の迂回輸出」です。
例えば中国で製造された製品をベトナムに一度輸出し、ベトナムで軽微な加工を施した後に“ベトナム製”として日本へ輸出するというものです。
このスキームにより、関税を回避しながら市場へのアクセスを維持することが可能になります。
この結果、日本の国内企業は“間接的に”ダンピング被害を受け続けてきました。
黒鉛電極が象徴的な事例
2025年3月、日本は中国製の黒鉛電極に反ダンピング関税を課しました。
これは鉄スクラップを溶かすための電炉で使用される重要な工業部材です。
中国からの直接輸入は減少したものの、その直後から黒鉛電極の一貫製造能力がない国々(例:タイ、インド)からの輸入が急増しました。
これにより「第三国を使った関税逃れ」が現実のものとなっていることが浮き彫りになりました。
日本政府が導入を検討する「60%ルール」
こうした状況を受けて、日本政府は制度改正を進めています。
焦点となるのが「原産性の基準」です。具体的には、以下のようなルールが検討されています。
- 製品の価値の60%以上が元々の課税対象国(例:中国)に由来
- 第三国で付加された価値が全体の25%以下
この2条件を満たす場合には、たとえ第三国経由であっても「実質的にはダンピング品」と見なして反ダンピング関税を課すという内容です。
これは、すでにEUが実施している基準と近いものになっています。
他国との制度比較:なぜ日本は遅れているのか?
実はG20の中で、このような「第三国経由対策」が未整備なのは日本とインドネシアだけです。
日本では第三国を経由したダンピングを防ぐためには、改めて個別の調査を開始し、再度関税を発動する必要があるのが現状です。
- 調査期間:約1年
- 損害認定には3年分のデータが必要
- 関係省庁の人員体制はわずか約40人
対して、アメリカでは300人超、韓国でも60人以上の専門部隊を持つなど、調査体制に大きな差があります。
制度だけでは足りない。運用力がカギに
数値基準を導入すれば、一見わかりやすく公平な制度のように見えます。
しかし、実際の国際取引は非常に複雑で、原産性や付加価値の定義にはグレーゾーンが多く存在します。
例えば「60%の価値が中国由来」と見なすには、原材料、製造工程、サプライヤーの証明書類などを総合的に分析しなければなりません。
さらに、迂回スキームも日々進化しており、制度の“抜け道”を突く手法が次々と生まれています。
そのため、数字のルールに加えて現場での運用能力と監視体制の強化が必要不可欠です。
未来への考察:制度改正は始まりにすぎない
反ダンピング関税の新制度は、日本がようやく世界基準に追いつこうとしている証拠でもあります。
しかし、それは「ようやくスタートラインに立った」という段階です。
これから本当に問われるのは、数字では割り切れないグローバルな商流の中で、どこまで実効的な措置を取れるのかという“現場対応力”です。
もしこの仕組みがうまく機能すれば、国内メーカーにとっては安価な輸入品との過度な価格競争から一歩抜け出すチャンスになります。
逆に制度が形骸化すれば、日本企業は“抜け道を許す国”として国際競争の中で後れを取る可能性もあります。
今後は関税法の改正だけでなく、貿易調査官の増員、AIによる原産地トラッキングなどテクノロジーの活用、通関制度全体の近代化といった広範な対策が求められることになるでしょう。
日本がグローバル競争の荒波の中で自国産業をどう守り、どう成長させていくのか。
その重要な一歩が、今回の反ダンピング関税の新制度なのです。