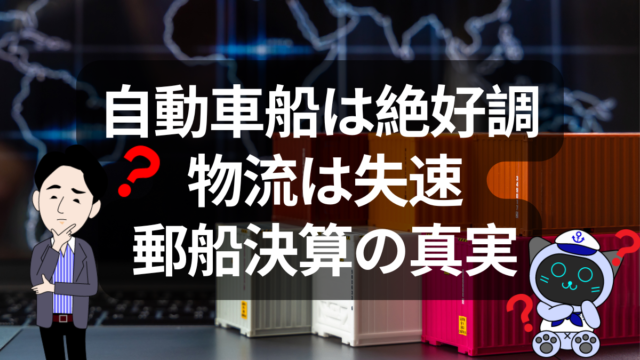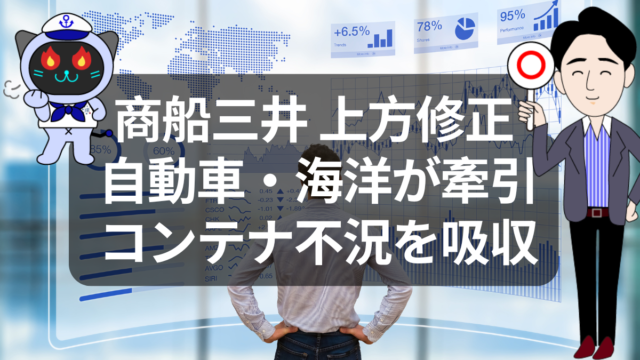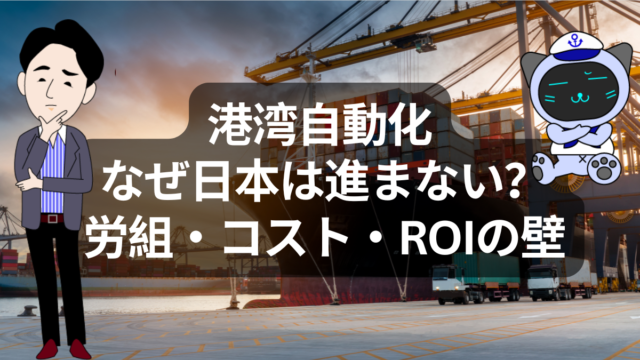投稿日:2025.10.28 最終更新日:2025.10.28
2025年、コンテナ船解撤が20年ぶり低水準!背景と海運業界・運賃への影響
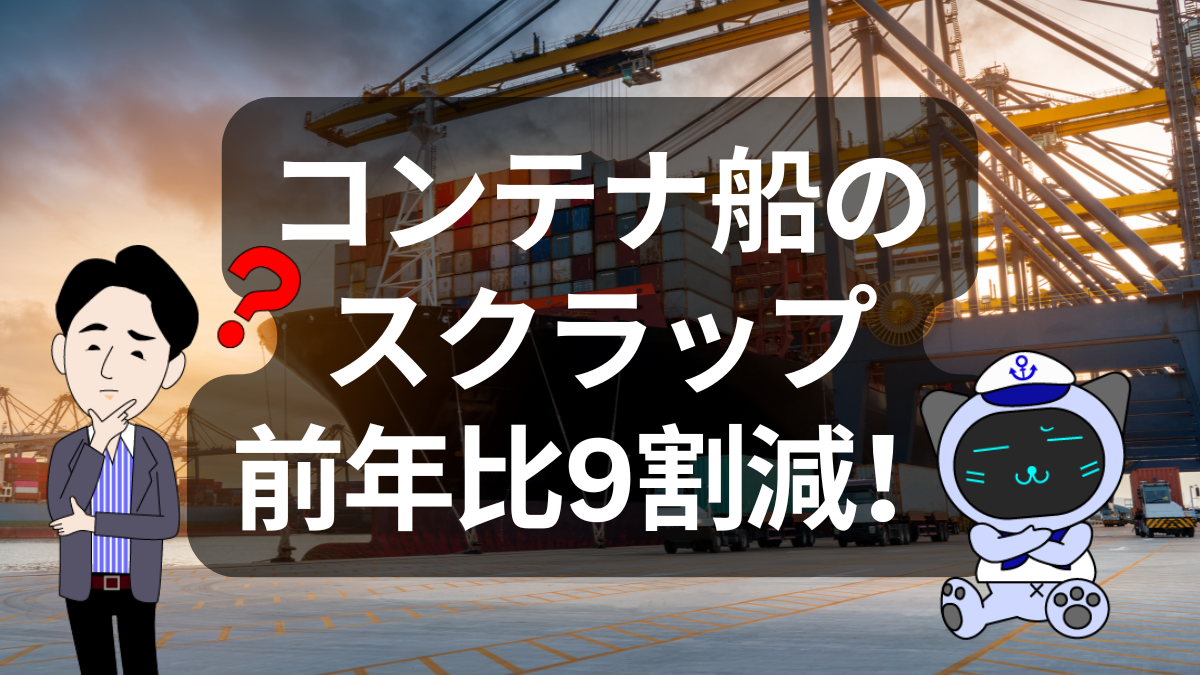
2025年の世界のコンテナ船の解撤(スクラップ)量が記録的な低水準に落ち込んでいます。
イギリスの海運調査会社クラークソンズによれば、2025年1~9月に解撤されたコンテナ船はわずか12隻・約5,000TEUにとどまり、前年同期比で約9割減少しました。
なぜこれほど船の解体が進んでいないのか、その背景と海運業界・海上運賃への影響を探ります。
CONTENTS
過去20年で最低水準となった2025年の解撤量
クラークソンズ・リサーチによると、2025年1〜9月の解撤実績は12隻・計5,000TEUほどで、2005年以来の低水準です。
特に300〜500TEU級の小型フィーダー船が中心で、大型本船はほとんど解体されていません。
通常は市況悪化で老朽船を処分して船腹整理を行いますが、2023〜2025年にかけてはその「逆の現象」が起きています。
老朽船が現役を続ける理由
老朽船が解体されない最大の理由は、用船市況(チャーター市場)の好調にあります。
高水準のチャーター料が続き、古い船を解体せず延命・転売した方が利益になる状況です。
また、以下のような要因も重なっています。
- 中古船市場での取引活発化
- 500〜1000TEU級の小型船に根強い需要
- 新造フィーダー船の建造が少ない
これにより、老朽船でも「まだ稼げる」ため、スクラップよりも運航継続が優先されています。
紅海リスクと減速運航がもたらす需給ひっ迫
2023年後半以降、紅海地域の地政学リスクによりスエズ運河経由の航路に混乱が発生。
多くの船がアフリカ南端・喜望峰を経由する長距離航路に切り替えた結果、航行日数の増加=実質的な船腹不足が発生しています。
加えて、燃料費節約や環境規制(EEXI・CII)対応として進む減速運航(スロー・スチーミング)も船腹の稼働効率を低下させています。
これらが複合的に作用し、「老朽船にも出番がある」状態を作り出しています。
新造船ラッシュとスクラップ停滞の矛盾
一方で市場では新造船ラッシュが続いています。
フランスのアルファライナーによれば、2023〜2025年に約730万TEU(世界の総船腹量の30%)が新規投入予定です。
それにもかかわらず解撤が進まない理由は以下の通りです。
- インド・バングラデシュでの鉄スクラップ価格の下落
- 現地通貨不安・リサイクルヤードの環境基準強化
- 2025年6月発効の「船舶リサイクル条約」による対応負担
これらの要因でスクラップ処理環境そのものが整わない状況にあり、船主は老朽船を手元に残しています。
将来の船腹過剰と運賃下落リスク
このまま解撤が進まなければ、世界的な供給過剰(オーバーキャパシティ)は避けられません。
市場分析では、2030年までに約450万TEUを削減しなければ均衡が取れないとの試算も出ています。
過剰船腹は最終的に海上運賃の下落圧力につながる可能性があります。
紅海情勢の影響で一部航路の運賃は底堅いものの、長期的には需給バランスの崩れが市場を軟化させる懸念があります。
まとめ:足元の好調に隠れるリスク
2025年のコンテナ船解撤量が20年ぶりの低水準にとどまっている背景には、用船市況の好調・地政学リスク・環境規制・スクラップ環境の混乱など複数の要因が重なっています。
短期的には合理的な延命策でも、長期的には供給過剰を生む「時限リスク」になりかねません。
老朽船の延命は一時的な利益をもたらしますが、海運業界全体の健全な船腹調整が進まなければ、再び運賃低迷に悩まされる可能性があります。
いま必要なのは、目先の好況よりも長期的な市場バランスの見極めです。