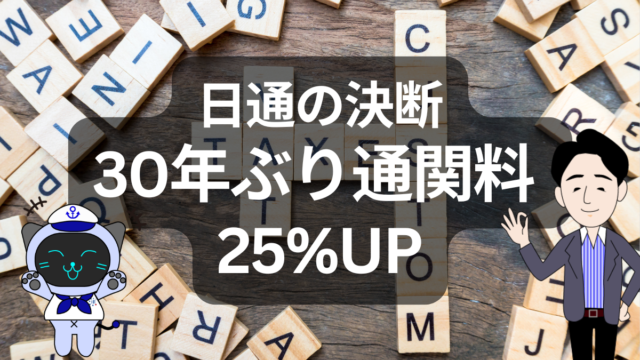投稿日:2025.10.29 最終更新日:2025.10.29
日米、造船協力で新時代へ!入港税の裏にある“アメリカ造船業復活”の戦略

2025年10月、日本とアメリカが造船分野での協力覚書(MOU)に署名しました。
建造能力の拡大、人材育成、技術革新、米国への投資促進など、一見静かな産業ニュースのようですが、その裏には「アメリカ造船業の復活」という国家戦略が隠されています。
トランプ政権が再び掲げる「アメリカ第一」の流れの中で、造船産業がどう再構築されようとしているのか。
そしてその中で、日本がどんな役割を果たそうとしているのかを解説します。
CONTENTS
日米、造船協力覚書に署名
10月28日夕方、東京の国土交通省で開かれた署名式で、金子恭之国交相とハワード・ラトニック米商務長官が署名しました。
「造船協力に関する覚書」が正式に交わされ、今後は日米両政府による「造船作業部会」が設置されます。
この部会では、次のテーマを中心に検討が進められます。
- 日米両国の造船能力拡大
- 米国海事産業基盤への投資促進
- 公船・商船など安全保障上重要な船舶需要の明確化
- 造船人材育成のための教育・研修強化
- AIやロボットなど先進的な建造技術の共同開発
造船業にも「AI」「ロボティクス」といったキーワードが並ぶ時代になりました。
もはや造船は“デジタルとリアルの融合産業”です。
日本側の狙い:安全保障としての造船
金子大臣は式典で次のように述べました。
「造船業は日米両国の経済と安全保障を支える、極めて重要な分野。両国が十分な建造能力を確保し、日米の船は日米で造ることが重要だ。」
エネルギー輸送、国防、物流、災害支援──いずれも海上輸送が基盤です。
つまり「造船が止まる=国家機能が止まる」。
日本はこのMOUを通じて、経済安全保障の要を再強化しようとしています。
アメリカ側の狙い:ゼロからの造船業再建
ラトニック商務長官は式典で率直に語りました。
「アメリカはかつて強力な造船業を持っていたが、今やほぼゼロだ。
日本と協力し再建したい。」
実際、米国内で大型商船を建造できる造船所はほとんど存在せず、商船建造分野では“空白”の状態です。
このため、日本の技術とノウハウを導入しながら再構築を図るのが狙いです。
背景にある「入港税」──アメリカの産業政策
2025年、トランプ政権は「入港税(Port Entry Fee)」を導入しました。
米国外で建造された船が米国港湾に入港する際に課税される制度で、自動車船では1隻あたり1億円超の負担になる例もあります。
その目的は明確です。
それは「アメリカで造られた船を増やすこと」。
つまり入港税は実質的な造船業保護策です。
ただし現状では造船所も人材も不足しており、制度の実効性を確保するために日本との協力が不可欠です。
技術革新と人材育成での協力
覚書にはAI・ロボットなどの先進技術や、人材育成分野での協力強化が盛り込まれました。
- AIによる造船工程管理
- 溶接ロボットの自動化
- デジタルツインによる設計支援
- 学生・技術者の交流や共同研修の創設
これにより、日本の若手エンジニアが米国造船所の再建に参加する可能性も出てきています。
まとめ:入港税から始まる日米の“造船同盟”
造船はかつて“古い産業”と呼ばれました。
しかし今、脱炭素・AI・地政学・サプライチェーン再構築の時代において、再び国家戦略の中心に戻りつつあります。
入港税によって「外から圧力」をかけ、覚書で「内から協力」を築く。アメリカはこの二段構えで造船業復活を狙っています。
日本はその最重要パートナーとして、技術と人材の両面で支援する立場に立ちました。
造船ルネサンス──日米が共に舵を切った新時代の幕開けです。