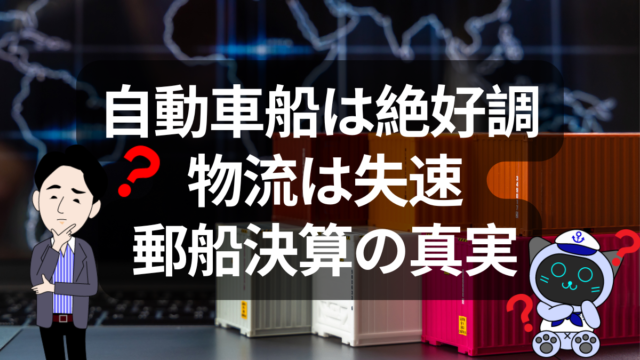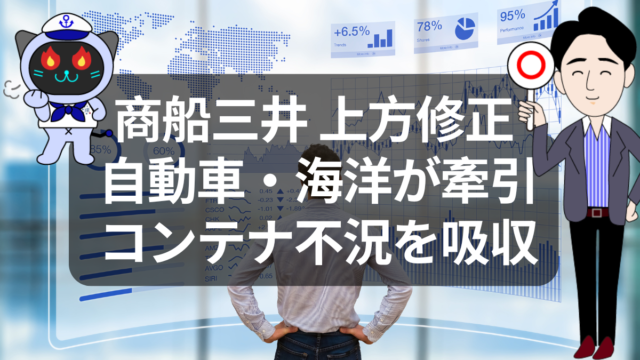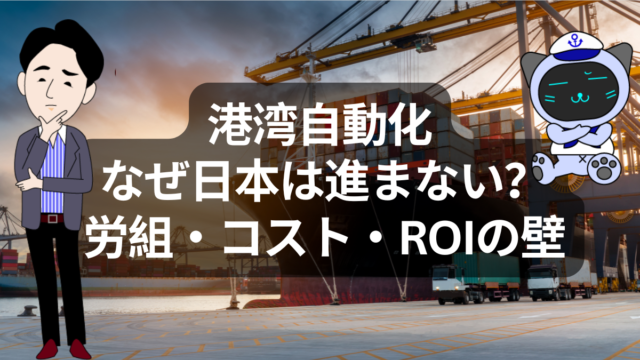投稿日:2025.07.18 最終更新日:2025.07.18
物流業界に激震、再編が止まらない!「2024年問題」と資本市場の圧力
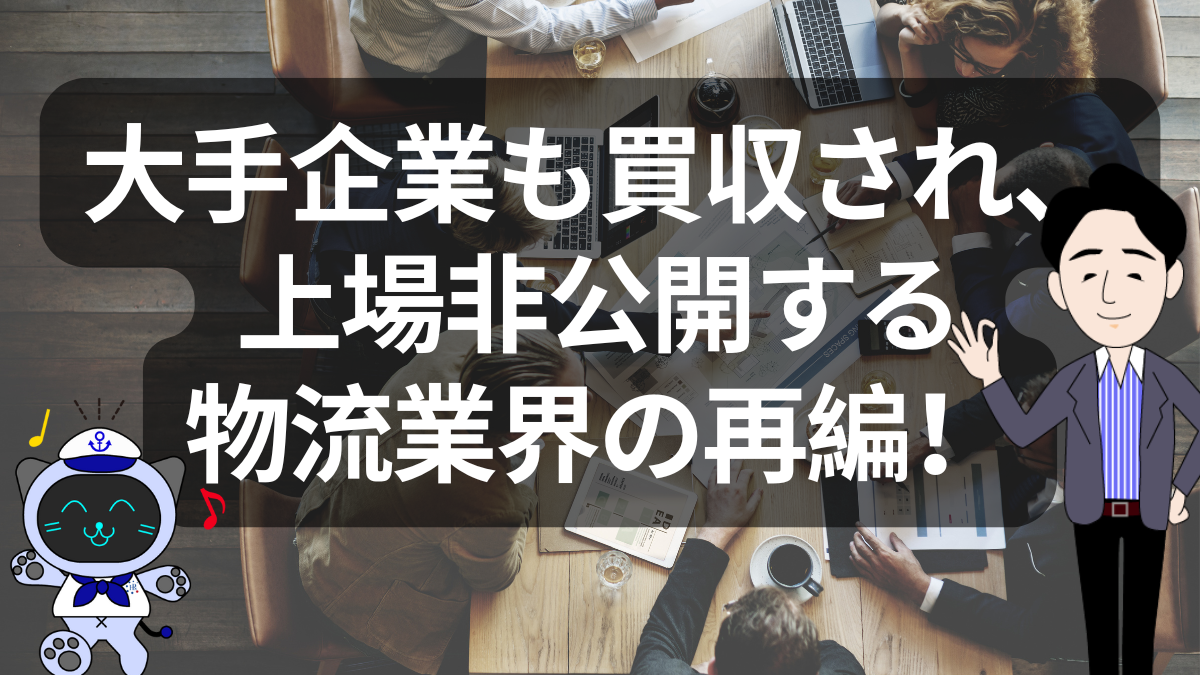
今回は、いま物流業界で急加速している「業界再編」の話です。
ここ数年、中小トラック会社のM&Aがじわじわ増えていましたが、2024年に入ってからは再編の動きが一気に本格化。
大手企業によるTOB(株式公開買い付け)や、MBO(経営陣による買収)=非公開化も続々と進行しています。
なぜここまで急速に再編が進んでいるのか。その背景を順を追って整理していきましょう。
CONTENTS
2024年問題が導火線に
ご存じのとおり、2024年4月から始まったドライバーの「時間外労働960時間規制」。
これにより、輸送力は下がり、人件費は上がるというダブルパンチを食らった中小企業は、事業継続に不安を抱えるようになりました。
この状況を背景に、事業承継やスケールメリットを狙ったM&Aが急増。
日本M&Aセンターの発表によれば、2024年の物流M&A件数は前年比25%増の121件。
数字としても「再編の加速」が明確に現れています。
大手企業も動き出した
注目すべきは、中小だけでなく大手を含めた本格的な再編フェーズに入っている点です。
たとえば、AZ-COM丸和HDによるC&FロジHDへのTOB(結果的にはSGHDが獲得)という案件。
これは物流業界初の「同意なき買収(敵対的買収)」とも言われ、証券会社や銀行も後ろ盾を見せるなど、市場の注目を集めました。
物流業界もいよいよ資本市場の論理から逃れられない時代に突入しています。
上場企業が次々に非公開化へ
物流業界では、上場企業が上場をやめる(非公開化)動きも続出。
背景には、東京証券取引所による「PBR1倍割れ企業への圧力」があります。
上場コストの増加に対し、株主の顔色より自由な戦略を選びたいという動きが強まっているのです。
実際に、以下の企業が非公開化を選択しています:
・トランコム ・日新 ・内外トランスライン ・日本コンセプト ・エスライングループ ・ロジスティード(米KKRと提携)
この流れは今後も続くと見られています。
外資系ファンドの参入
再編を加速させているのが、外資系ファンドの存在です。
・トランコム、日新 → ベインキャピタル(米系) ・日本コンセプト → J-STAR(国内ファンド) ・ロジスティード → KKR(米系) ・内外トランスライン → IAパートナーズ(元DBJ系)
こうしたファンドがMBOパートナーとして非公開化を推進。
資本効率やキャッシュ創出を重視した再設計が進んでいるのが今の物流業界です。
迫られる事業ポートフォリオの見直し
「アクティビスト」と呼ばれる“もの言う株主”の存在も再編を後押ししています。
彼らが企業に求めるのは主に2つ:
・不要な不動産の売却による資産圧縮 ・中核以外の事業売却による集中と効率化
その結果、物流会社も「何を残し、何を手放すか」という判断を迫られているのです。
まとめ:
これまでの物流業界では、人手不足やドライバー問題が主要課題でした。
しかし今、話題の中心は「資本構造」や「株主の意向」へと移っています。
つまり、物流業界は“ヒトの問題”から“カネの問題”へと課題が移行しているのです。
この動きは今後も続くでしょう。
いかに柔軟に資本と組み、成長戦略を描けるかが、企業の明暗を分ける時代に突入しています。
この再編の波をどう乗りこなすのか。現場のプレイヤーも、経営サイドも、今こそ本気で考えるべきタイミングです。