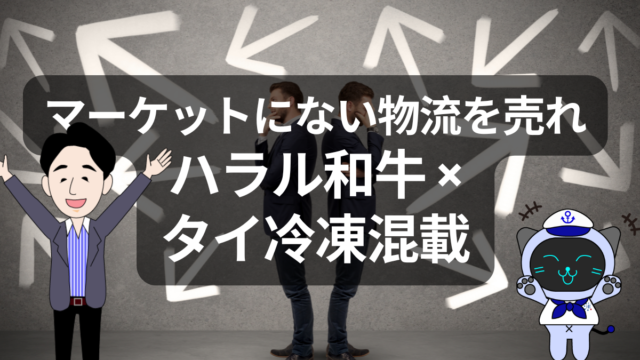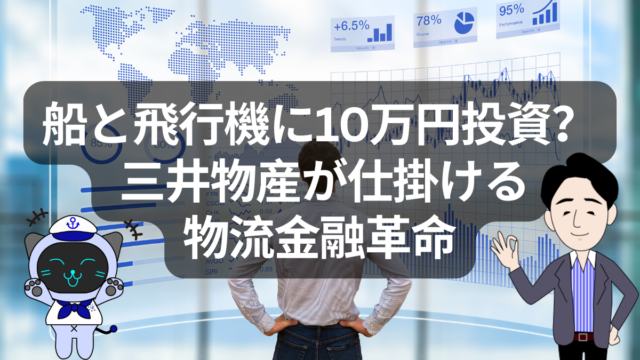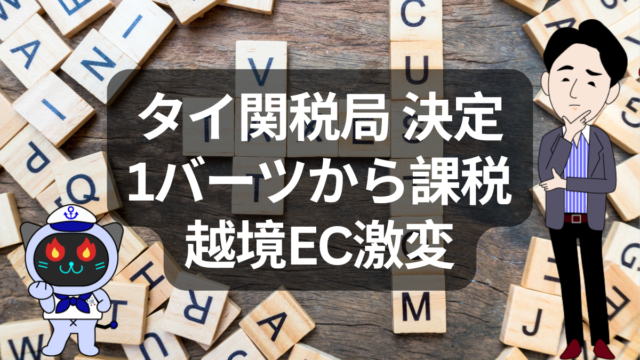投稿日:2025.08.05 最終更新日:2025.08.05
釜山 vs 日本の港湾戦略〜ハブ港を目指す条件とは?
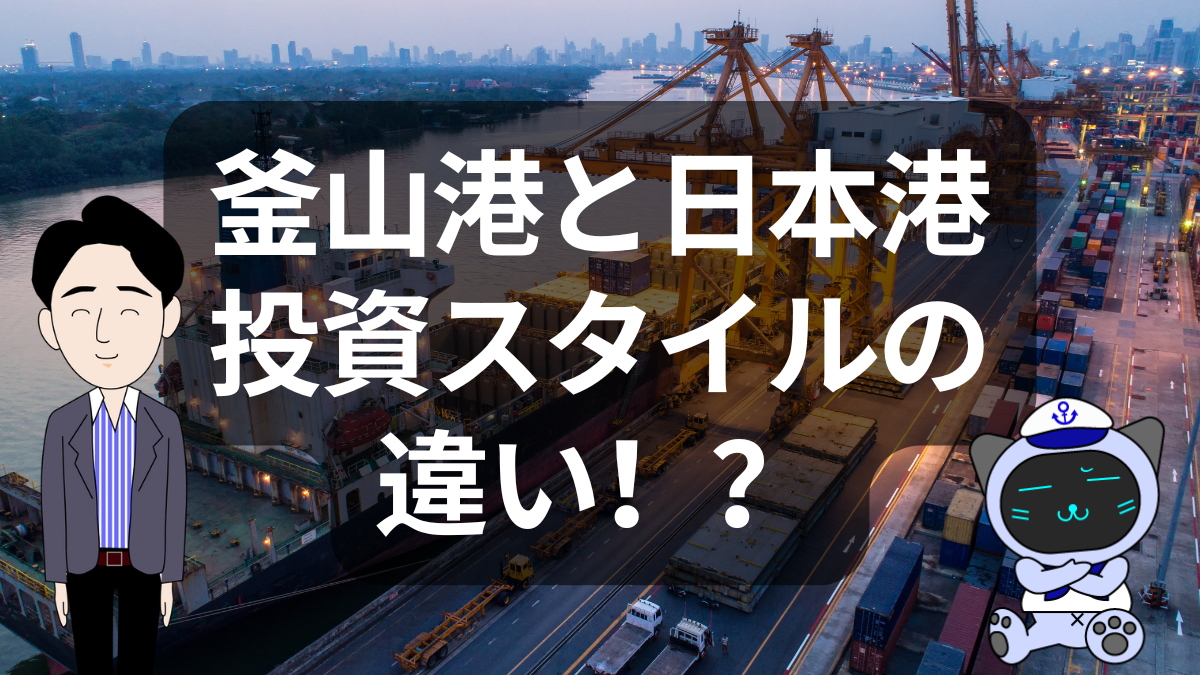
今日は韓国・釜山港が新たなフィーダー専用ターミナル建設とデータ共有システムの開発に本腰を入れたというニュースを取り上げながら、日本の港湾投資の現状についても考えてみたいと思います。
CONTENTS
釜山港、トランシップで攻めに出る
韓国の釜山港は、2025年7月、総額5.73億ドル(約900億円)を投じて新たなフィーダー船専用ターミナルの建設を発表しました。
あわせて、Port-i(ポートアイ)というリアルタイムのデータ共有プラットフォームも開発中で、積み替え貨物の流れを可視化・高速化する狙いです。
このターミナルは年間150万TEUの能力を持ち、2030年の開業を予定。
2バース(各2,000TEU対応)に加えて、ブレークバルク貨物にも対応できる桟橋も備えます。
釜山港は2024年にトランシップ貨物が1,350万TEUと前年比9%増。
これは港全体の貨物の55%が積み替え貨物であることを意味しており、まさに“トランシップ拠点”としての地位を確立しつつあります。
トランシップの本気度、BPAの狙い
釜山港湾公社(BPA)の幹部は、「Port-iにより他の船社も釜山を利用しやすくなる」と述べており、すでにMSCが釜山で取り扱うコンテナの80%がトランシップ貨物だそうです。
データ共有で不安のあった荷主・船社への対応として、このプラットフォームは商用ではなく港湾公社が運営・管理する方針。非常に戦略的です。
🇯🇵では、日本の港湾はどうなのか?
結論から言うと、日本の港湾政策は「ハードよりソフト」重視に偏っているのが実情です。
ソフト面では…
・TradeWaltz、CyberPortなどの電子化やデジタル連携の取り組みは継続中。
・港湾運営会社制度による民間主導の効率化も進んでいます。
・AIや5Gを活用したゲート効率化も実証段階に入っています。
ハード面では…
・フィーダー専用ターミナルの建設はほぼゼロ。
・中長期的なトランシップ戦略を前提とした設備投資も皆無に近い。
・複数港の連携やゲートウェイ設計の再構築といった国家戦略レベルの視点が欠けています。
地政学・体制の違い
| 観点 | 日本 | 韓国(釜山) |
|---|---|---|
| 地理的位置 | 貨物の終着地が多く、トランシップ比率が低い | 北東アジアの中継点として最適 |
| 港湾管理体制 | 港ごとに自治体や運営会社が分散 | BPAが一括運営・整備 |
| 投資の意志決定 | 民間主導・採算重視 | 国家主導・先行投資型 |
まとめ
釜山は明らかに「選ばれる港」としての努力を続けています。一方で日本の港は、“来る貨物を処理する港”のままではいられない。
トランシップを呼び込むには、ハードもソフトも両輪で動かすべきフェーズに入っています。
今後、例えば北陸や九州などの地方港がフィーダー貨物の中継ハブとして注目される可能性もあります。
そこに向けて、日本の港も次の一手が問われています。